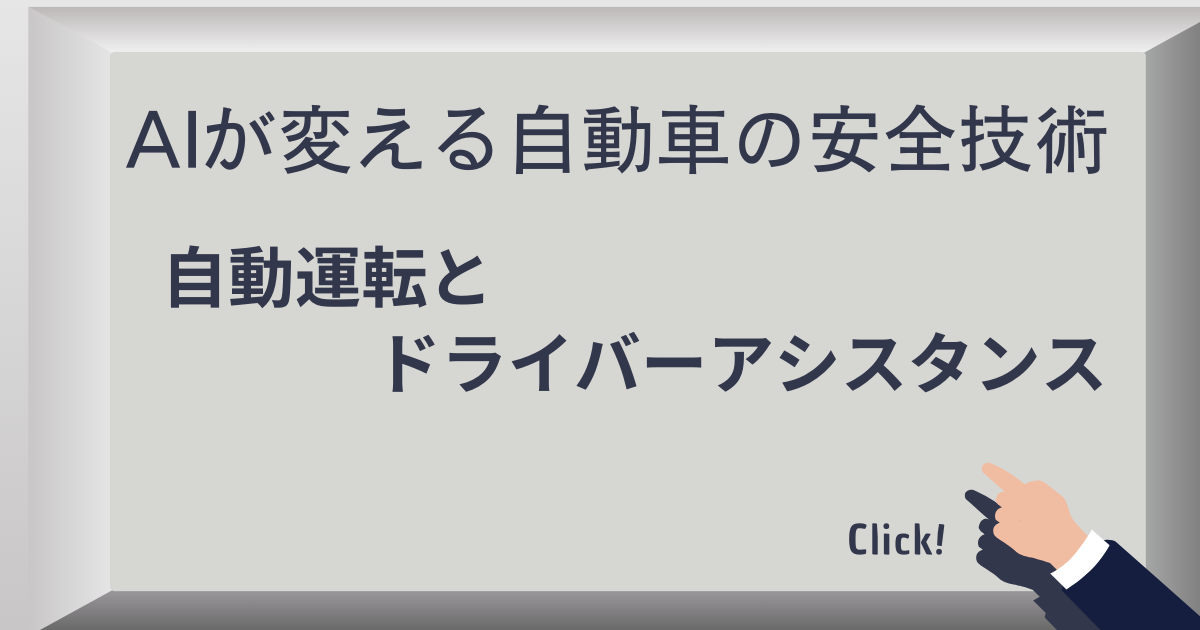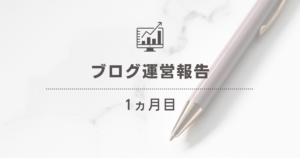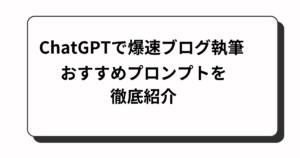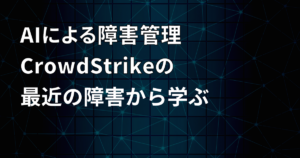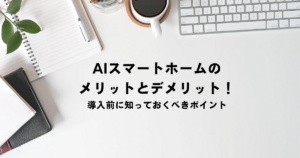自動車には多くのコンピューターが搭載されており、私たちが安全に運転するためにさまざまなサポートをしてくれています。この記事では、自動車に搭載されているAI技術について紹介します。
生成AIと一般的なAIの違い
まず、生成AIと一般的なAIの違いをご存知でしょうか?ChatGPTに聞いてみたところ、以下のような回答が得られました。
生成AI(ジェネレーティブAI)は、新しいデータ(例えば、文章や画像)を生成するAI技術です。例として、ChatGPTやDALL-Eがあります。一方、一般的なAI技術は、既存のデータを分析し、パターン認識や予測を行うために使用されます。例として、画像認識や自然言語処理があります。生成AIは創造的な作業に強く、一般的なAI技術はデータ分析や特定タスクの解決に優れています。
自動運転システムについて
次に、自動車に使われているAI技術として、まず思い浮かぶのは自動運転でしょう。日本の主要なメーカー3社の自動運転技術について調べてみました。
トヨタ
- トヨタは「Teammate」というブランド名で自動運転技術を開発しています。これには、高度なドライバー支援システム(ADAS)やレベル2の自動運転技術が含まれます。特に高速道路での自動運転や自動駐車システムが特徴です。
トヨタ Highway Teammate: レベル2+の自動運転技術
- 高速道路での自動運転機能に加え、渋滞時や一般道での運転支援機能も備えている。
- 2020年頃に実用化をめざした実験車を公開
- 将来的には、レベル4の自動運転技術の実現を目指す
ホンダ
- ホンダは「Honda Sensing Elite」というシステムを展開しており、レベル3の自動運転技術を含んでいます。このシステムは、高速道路でのハンズオフドライビングやトラフィックジャムパイロットなどの機能を提供します
ホンダ Honda SENSING 360: レベル3の自動運転技術
- 2021年4月に発売した「レジェンド」に搭載
- 高速道路でのハンズオフ運転が可能
- 渋滞時や一般道での運転支援機能も備えている
日産
- 日産は「ProPILOT」というブランド名で自動運転技術を提供しています。レベル2の自動運転技術を含み、高速道路でのアダプティブクルーズコントロールやレーンキープアシストが主な機能です。
日産 ProPILOT 2.0: レベル2の自動運転技術
- 速道路でのアダプティブクルーズコントロールやレーンキープアシストに加え、車線変更支援機能などを追加
- 2022年3月に発売した「アリア」に搭載
| メーカー | 技術名 | レベル | 主な機能 |
| トヨタ | Highway Teammate | レベル2+ | 高速道路での自動運転、渋滞時・一般道の運転支援 |
| ホンダ | Honda SENSING 360 | レベル3 | 高速道路でのハンズオフ運転、渋滞時・一般道の運転支援 |
| 日産 | ProPILOT 2.0 | レベル2 | 高速道路でのACC・LKA、車線変更支援 |
ドライバーアシスタンス
次に、ドライバーアシスタンス機能におけるAI技術の具体例をいくつか挙げてみます。
- 自動緊急ブレーキ(AEB)
-
センサーやカメラからのデータをAIで分析し、衝突のリスクを判断して自動的にブレーキをかけます。
- アダプティブクルーズコントロール(ACC)
-
AIが前方車両との距離や速度を継続的に計算し、最適な速度を維持します。
- レーンキーピングアシスト(LKA)
-
カメラの映像をAIで解析し、車線を維持するためのハンドル操作を補助します。
- ブラインドスポットモニタリング(BSM)
-
AIが側面や後方の車両を検知し、ドライバーに警告を発します。
- ドライバーモニタリング:
-
AIがドライバーの顔の向きやまばたきの頻度を解析し、疲労や注意散漫を検出します。
安全技術パッケージについて
また、日本の自動車メーカーが提供する主要な安全技術パッケージについても調べました。
トヨタ「Toyota Safety Sense」
- 自動ブレーキシステム、車線維持支援、自動ハイビームなどを含む総合的な安全パッケージです。
ホンダ「Honda Sensing」
- 衝突軽減ブレーキ(CMBS)、車線逸脱警告(LDW)、アダプティブクルーズコントロール(ACC)など、先進的な機能を搭載しています。
マツダ「i-Activsense」
- スマートシティブレーキサポート、ブラインドスポットモニタリング、後退時交通警告など、多様な安全機能を提供しています。
スバル「EyeSight」
- 前方の車両との衝突を回避するブレーキ支援や、車線内を保持する支援機能が特徴的で、高い評価を受けています。
まとめ
車に使われているAI技術は多岐にわたり、日々進化を遂げています。これらの技術を組み合わせることで自動運転が可能となります。日本では、2023年3月にレベル4の自動運転技術が初めて認可され、特定の条件下で完全に自動化された運転が可能となりました。福井県の永平寺町での事例では、特定のルートで遠隔監視下での自動運転サービスが行われ、最大速度は12 km/hに制限されています 。
一方、商業的に利用可能なシステムの多くはまだレベル2の自動運転技術に留まっており、高速道路でのアダプティブクルーズコントロールやレーンキーピングアシストなどの機能を提供していますが、完全な自動運転には至っていません 。
世界では、レベル4の自動運転技術の公道試験が進んでおり、GoogleのWaymoやBaiduなどの企業が先導しています。これらの企業は、特定の条件下で完全に自動化された運転が可能な車両をテストしていますが、広範な商用展開にはまだ至っていません 。
完全自動運転技術が確立されれば、物流システムが大きく変わる可能性があります。これからの未来が非常に楽しみですね!